今朝、車に乗り込むと外気温は22℃を示していました。 日中はまだ気温が高いのでしょうけれども、かなり涼しくなりましたね。 去年は11月頃まで暑かった気がしますが、今年は秋の訪れが早そうです。
昨日は夕方に駅前にある楽器屋にギターの弦を買いに行くついでにシアトルズカフェ(世紀名称シアトルズベストコーヒーと言うらしい)に寄りました。 久しぶりにカフェモカを飲みましたが、ここのやつが他のコーヒーショップのものに比べて一番美味しいと思うんです。
レジ待ちしてる時に吊り下げられているオーナメントを見ると、ハロウィーンの装いがされていました。

もうそんな季節かと。
ハロウィーン
そもそものハロウィーン
ハロウィーンはもともとケルト民族の秋の収穫を喜ぶ祭りだったらしい。 それがアメリカの祭りとして定着したとの事。 ハロウィン - Wikipedia
憧れのハロウィーン
僕は1983年生まれなんですが、子供の頃、ハロウィーンを祝う風潮は周りにありませんでした。 洋画を見て、子どもたちが夜に家々を練り回り、お菓子をもらっている場面を見ると、どうしてこの素晴らしい祭りが日本にはないのかと悔しかったものでした。
しかし1991年生まれの彼女に言わせると、ハロウィーンは子供の頃から当たり前にあったらしい。
でも子ども達が「トリックオアトリート」と夜の住宅街で言っているのを聞いたことがないので、おそらく、子供心に肝心だった、お菓子をもらう方の形態は浸透していないようだ。 それとも、都会の方では実は昔から一般的だったりするんだろうか。
仮装大会としてのハロウィーン
昨日、彼女は彼女の友達と、ハロウィーンの日の仮装の話題で盛り上がっておられました。 そろそろ街のビラに「ハロウィーン仮装大会」の文字が踊り始める頃だと思います。
新しい文化というものがどういう風に世の中に浸透していくか、ハロウィーンを想うと興味深いです。
プレイヤーが増える→大会が始まる→シーンが盛り上がる→プレイヤーが増える・・・のループでシーンに関わる人が増えていく。 そうするとそこに資本が投下されて、さらに加速度的に盛り上がって行くという。
去年は仮装大会優勝賞金3万円というチラシを見ました。仮装する気合も入ろうというものです。 とても素晴らしい事だと思います。
お祭りは多い方がいいと思うし、何しろハロウィーンの夜の非日常感は見てて面白いです。
今となっては当たり前のクリスマスケーキやプレゼント、バレンタインもこんな感じでいつの間にか浸透したんだろうなあと思うと感慨深いですね。
そう言えば最近、お年玉的なお盆玉という物をはやらせようとする動きがあるようです。
うちはカトリックなんですが、お盆になると何故か祖父母がお小遣いをくれました。 お盆にお小遣いってどこ発の伝統なんだろう。当時はただただ嬉しかっただけですが・・・。
しかしすっかり大人になってしまった今、子どもたちには悪いけど、お盆玉は流行らなくてもいいかな(遠い目)
更新情報をお届けします


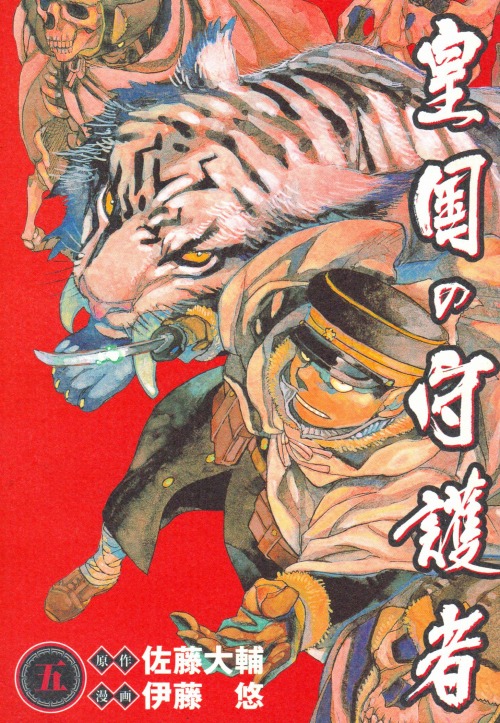
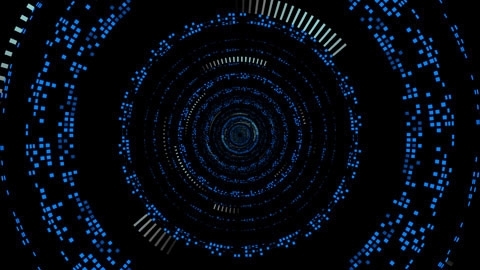




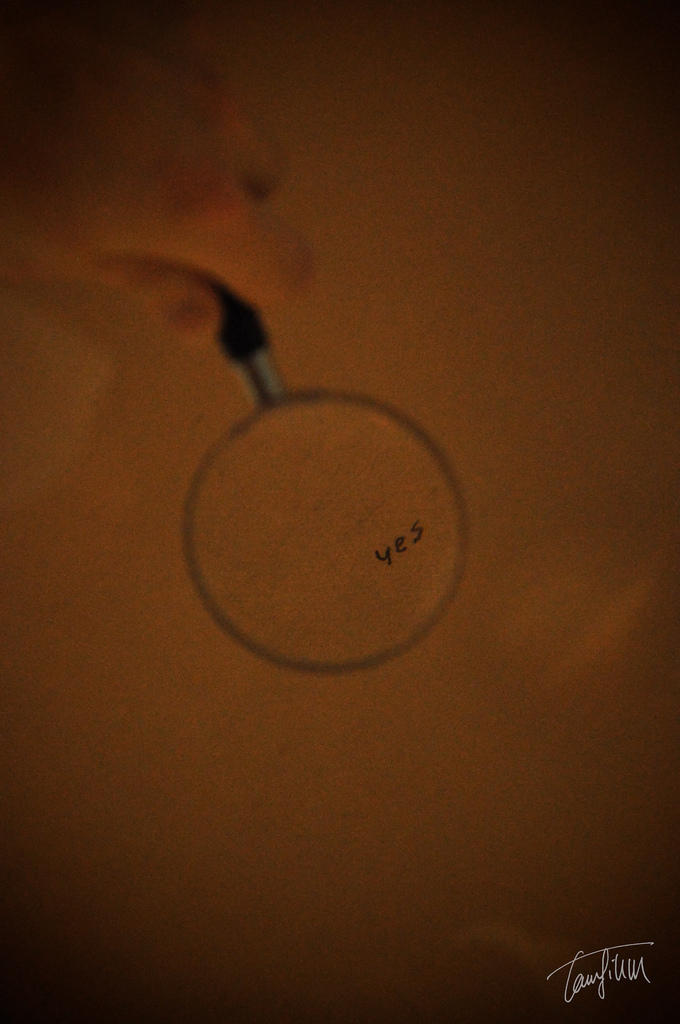












この記事へのコメントはありません。