この記事の目次
近頃は将棋を打てない人が増えているようなので、将棋の話などをしても共感を得られない事が多いかも知れない。
先日、友人と久しぶりに将棋で遊びました。
将棋には長い歴史の中でつちかわれた「定石(じょうせき)」というものがあって、「こういう場合は、こう駒を動かすのがいい」というのが結構決まっているものなのです。
僕は最近ぜんぜん将棋をやっていなかったので、この定石を忘れていて、わりと無茶苦茶な感じで勝負が始まりました。
結果は、辛くも勝利する事が出来たのですが「もうこういう戦いはしたくない」と心から思った一局になりました。
地盤を固める重要性
将棋のプレイスタイルにも色々なものがありますが、僕はわりと守りを固めてから攻めるタイプです。
かなり昔からこのプレイスタイルは変わっていないので、意外と自分は根っからの慎重派なのではないかと思います。
なぜ、こうなのか。
今回めちゃくちゃな一局を経て分かったのですが、単純に
攻めるのに集中させて!
という事だったのか。と気づきました。
将棋というのは、倒した敵の駒が自分の手駒になるという性質上、実に自由度の高いゲームです。
敵の駒を倒して手駒にすると、盤上の好きなところに置くことができます。
逆に言えば盤上のどこにでも敵が出現するというのは恐ろしいもので、人間の頭ではとてもじゃないですがその全てのパターンを追う事はできません。
まずは守りについて安心できるように固めていないと、相手から手駒を打たれる度に、守りの事と攻めの事を両方、全力で考えなくちゃいけないのです。
これはミスの許される幅が非常に小さくなることにつながります。
そしてこの状況は攻める姿勢にも影響します。
将棋では時に自分の駒を犠牲にしても戦局を切り開く必要があるものですが、それができない。
相手に駒が渡ることで不確定要素が更に増えるからです。
そのため守りも攻めも中途半端な状況で、かなりの長い時間をかけて一局を終わらせることになりました。
拳で殴り合うのと同じ
定石や、既存の守りの陣形というのは、将棋が開発されてからこれまで、将棋に人生を捧げた人たちの汗と涙を引き換えにして発見されたものです。
これは人類の叡智(えいち)の一つです。
ある陣形、ある定石というのは勝利の為の「システム」であり、とりあえず作ってしまえば戦いの中の一定範囲をそれに預けてしまえる様なものなのだと思います。
言うなれば戦いに勝つための要塞やマシンガンの作り方、というのが先人によって既に完成されているようなものです。
なのにそれを用いずに戦うというのは(格闘技ずぶの素人が)裸になって拳で殴り合うような事です。
かくして、お互いが完全に疲弊し終わったころ、勝負は決まったのです。
有名な「孫子の兵法」の中に 「勝兵はまず勝ちてしかる後に戦いを求め、 敗兵はまず戦いてしかる後に勝を求む。」
という言葉があります。
何にしてもそうですが世の中の物事、上手く運ばせようと思えばまず立ち止まり一考したのちに取り掛かる、というのは非常に大切な事だなあと。
体力や瞬発力に自信のあった20代を越えて今、その自信を失い、改めてそう思う機会が増えてきた気がします。
人生にも定石はある
将棋にかぎらず、人間の叡智というのは「本(文字)」という形でつちかわれてきました。
人の生き方、考え方、悩みや苦しみとの相対(あいたい)の仕方など、さまざまな定石がさまざまな形で著されています。
僕ら、まずこれらを学ぶことによってこれからの時代を生きるためのスタートラインに立つことができるのかもな。と最近は思います。
まず物の仕組み(定石)を学ぶことで、余計な事を考えず、攻める事に集中できるものではないだろうかなと。
最近こんな話を見ました。
あるところに数学が好きな男がいた。 その男は貧しかったのだろうか、学校には行っていなかった。 そして長い時間をかけてすごい発見をしたので発表したら、実はなんてことのない中学校でも習う2次方程式の解の公式だった。 既存のものを知らないと新しいことを発見するのは難しく徒労に終わる可能性が高い。
また、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインという人はこんな事を言ったそうです。
私の言語の限界が世界の限界を意味する
かつて学術機関が全ての知識を掌握していた頃と違い、今は学校になんぞ行かなくても、いくらでも学ぶ事のできる時代です。
文字で学んだ事は所詮、知識にすぎないかも知れませんが、ないよりはある方がマシなのは事実だと思うので、生きている内はこれからもたくさんの本を読みたいものだ。
と近頃よく考えています。
本日もG線上のきりんにおこしいただきありがとうございます。
生身の拳で殴り合ったあとに血だらけの二人が川原に倒れ込み
「へへ、お前、なかなかやるじゃねえか。」というのも友情を深めるという事においては良い物だと思います。
ところでこういうシチュエーションってよく目にしますけど、元々のオリジナルってどの作品なんだろう。
更新情報をお届けします




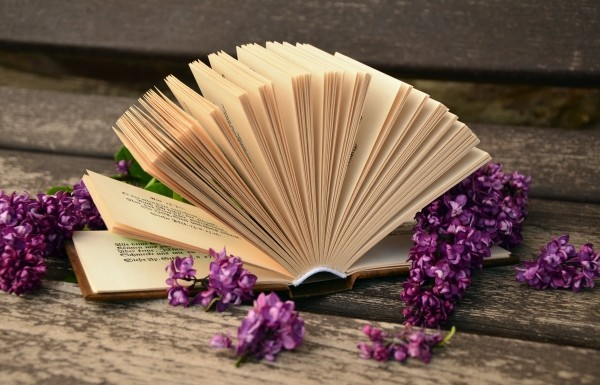



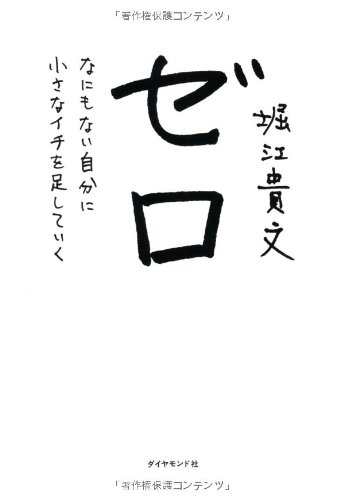







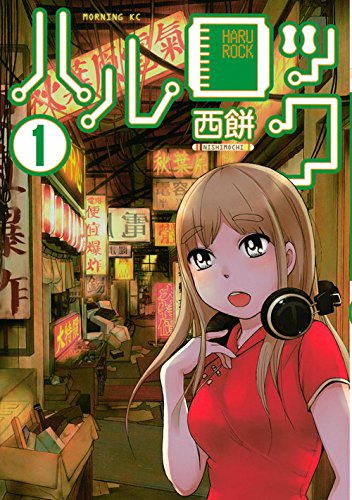




この記事へのコメントはありません。